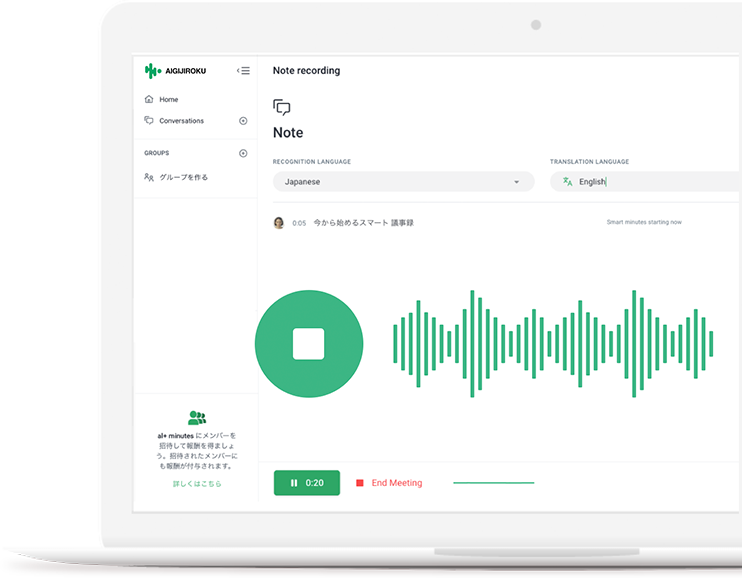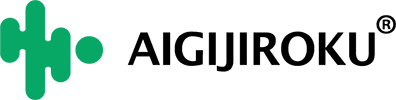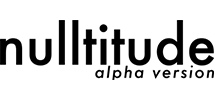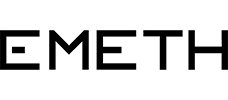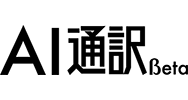小売業の仕事をされている方は「DX推進は何をしたらいいの?ポイントや成功事例を知りたい」と思うことがあるのではないでしょうか。
ビジネスにおけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がAIやデジタルシステムを活用して、業務改善や新しいビジネススタイルの創出をすることです。効率化に限らず、組織改革やアナログシステムからの脱却を実現させることも指しています。
今回は小売業に焦点をあてて、DXを推進するメリットや方法を紹介します。具体的な導入事例も解説しているので、導入を検討している方は参考にしてみてください。
目次
小売業界の現状とDX推進が必要な理由

昨今の小売業界は、次のような課題を抱えています。
- 深刻な人材不足
- トレンドの変化
- 既存システムの老朽化
- 蓄積すべきデータの不足
こうした課題を解決する方法の1つとして求められているのが、DX推進です。まずは小売業界の現状を知って、なぜDX推進が必要なのかを理解しましょう。
深刻な人材不足
小売業界の多くは人手不足に陥っていると言われています。帝国データバンクの調査によると、「非正社員の人手不足割合」の上位10カテゴリーのうち、3つに小売業がランクインしています。
- 各種商品小売:52.3%
- 飲食料品小売:48.7%
- 繊維・繊維製品・服飾品小売:42.9%
このように小売業の4割以上の企業が人手不足を感じているのが現状です。少子高齢化が進む現代において、深刻化していく人材不足に対応するには、DX推進による業務効率化や生産性の向上が欠かせません。
トレンドの変化
小売業は人材不足に加えて、ユーザーのニーズの変化による影響を大きく受けています。2000年代以降、インターネットの急速な普及によりECサイトの利用が拡大し、実店舗で買い物をする人が減少しました。さらにコロナ禍によって、通販サイトの利用者が増え、来客数が減少した時期もあります。
顧客の購買ニーズは時代とともに変化します。このトレンドの変化に対応するためには、DXを推進しニーズに沿った新たなビジネス手法を取り入れる必要があるのです。
既存システムの老朽化
小売業界においては、既存システムの老朽化が課題となっているケースも少なくありません。移り変わっていく顧客のニーズに応え続けるためには、時代に合わせた体制やシステムの構築が重要です。顧客ニーズへの対応ができていないと、集客や売り上げの低下にもつながりかねません。
また、既存システムを長期にわたって運用していた場合、構築した際の担当者が退職していなくなってしまい、内部構造が不透明になる「システムのブラックボックス化」が生じるケースも考えられます。
ブラックボックス化してしまったシステムは、時間の経過とともにレガシー化していき、その状態を解消するためには大きなコストと時間がかかるようになります。こうした状況を防ぐためにも、DX推進は急務とされているのです。
蓄積すべきデータの不足
移り変わりゆく顧客ニーズを捉え、新たな商品やサービスを開発するためには、データの蓄積と活用が欠かせません。しかし、老朽化したシステムでは有効なデータが取得できなかったり、蓄積されていたデータを新しいシステムに移行できなかったりといったケースが生じることも考えられます。
DX化を進め、データ活用環境を整備することは、これからの時代に事業を成長させていくために必要不可欠だと言えるでしょう。
小売業界の多くは人手不足に陥っていると言われています。帝国データバンクの調査によると、「非正社員の人手不足割合」の上位10カテゴリーのうち、3つに小売業がランクインしています。
- 各種商品小売:52.3%
- 飲食料品小売:48.7%
- 繊維・繊維製品・服飾品小売:42.9%
このように小売業の4割以上の企業が人手不足を感じているのが現状です。
また小売業は人材不足に加えて、ユーザーのニーズの変化による影響を大きく受けています。2000年代以降、インターネットの急速な普及によりECサイトの利用が拡大し、実店舗で買い物をする人が減少しました。さらにコロナ禍によって、通販サイトの利用者が増え、来客数が減少した時期もあります。
このような人材不足解消・時代の変化に対応するためには、新たなビジネス手法である「DX」を進めることが欠かせません。
小売業がDXを進めるメリット

小売業がDXを進めるうえで得られる3つのメリットを紹介します。
- 業務効率化が期待できる
- 顧客満足度が向上する
- コスト削減ができる
「DX推進の重要性はわかるけれど、具体的な効果がイメージできない」という方は、企業が得られるメリットを参考にしてDXを進めましょう。
業務効率化が期待できる
1つ目のメリットは業務効率化が期待できることです。例えば、今まで手作業で行われていた勤怠管理やデータ管理などの業務にITを導入することで、従業員の作業負担を軽減できます。
そして効率化によって業務フローの再構築が可能になり、今まで時間を割けなかった人材育成や、従業員のスキルを活かせる適正な人材配置がしやすくなるでしょう。
顧客満足度が向上する
2つ目は顧客満足度の向上を見込めることです。セルフレジや電子決済サービスの導入により、会計業務が効率化できれば従業員は接客業務に専念できます。結果として、顧客と密なコミュニケーションが取れるようになれば、接客のクオリティが上がるでしょう。
顧客にとっても「店員さんが忙しそうだから声をかけづらい」などの不満が無くなり、顧客満足度の向上につながるはずです。顧客のニーズに応えることで「このお店にまた来たい」と思ってもらえたり、良い口コミが広がったりと売上向上も期待できます。
コストを削減できる
3つ目はコストを削減できることです。DXにより業務を改善すれば、人件費や商品の保管にかかるコストが軽減されます。
またAIや在庫管理システムを導入すれば、販売状況や在庫を逐一確認できるので、無駄な発注やロスを防げます。「倉庫に過剰に在庫があって管理が大変」「商品の保管にもコストがかかる」など、在庫にまつわる課題も解決できるでしょう。
小売業DXの具体的な方法は?

ここでは小売業DXの具体的な方法を5つご紹介します。
- 店舗業務の効率化
- ECサイトの運用
- OMOの導入
- 倉庫内業務の効率化
- マーケティングの活用
具体的なDXの進め方について疑問をお持ちの方は、参考にしてみてください。
店舗業務の効率化
1つ目の方法は店舗業務の効率化です。昨今ではセルフレジや無人レジ、キャッシュレス決済の導入が増えつつあり、以下のスタイルが多く見られるようになりました。
- 商品をまとめてスキャンし、自動会計する
- 店員が商品をスキャンし、会計はセルフレジで行う
- 商品のスキャンから会計まですべてセルフで行う
上記のスタイルに変更すると、店員にかかる会計業務の負担を削減できます。すべての会計業務を自動化するためにはある程度のコストがかかるので、まずはセルフレジを数台導入するなど、段階的に試してみてもいいでしょう。
ECサイトの運用
2つ目の方法はECサイトの運用です。ECサイトと店舗を組み合わせれば、時間や場所の制限がなくなり、より多くの顧客に認知されやすくなります。
「ECサイトを作る余力やコストがない」という場合は、BASEやShopifyといった、安価で簡単にECサイトを作れるツールを活用してもいいでしょう。徐々に売上が出始めたら、自社のECサイトを大規模なコストをかけて構築していくのもひとつの手です。
OMOの導入
3つ目はOMOの導入です。OMOとは英語の”Online Merges with Offline”の略です。実店舗とECサイトを融合して、オンラインとオフラインの境目をなくした販売戦略のことを指します。
例えば、アプリやECサイトで商品を注文し、店舗で受け取るのもOMOのひとつです。OMOは、顧客の利便性の向上だけでなく、来店へのきっかけを作る戦略としても効果的です。店舗に来客してもらえれば、店員の接客によって購買意識を高めたり、「ついで買い」を促したりすることが可能となります。
ECサイトを作る際にOMOも視野に入れ、店舗への来客を増やす施策を立てるといいでしょう。
倉庫内業務の効率化
4つ目は倉庫内業務の効率化です。DXの一環として在庫管理システムやAIを導入すれば、倉庫内の在庫の適正管理が可能になります。
さらに正確な在庫数の把握や発注ミスを防ぐ効果も期待できます。まずは在庫数を知るためのデジタルツールを導入し、徐々に保管や発注業務も自動化してDXを拡大していきましょう。
マーケティングデータの活用
5つ目はマーケティングデータの活用です。具体的には顧客情報や購入履歴などのデータを蓄積・分析し、マーケティング戦略に生かすことを指します。
店舗での接客では簡易的な購買データしか残りませんが、ツールを使ってデータを収集すれば、より高度な情報を記録できるようになります。例えば、自社アプリを導入して年代や性別、購入履歴をもとに、顧客ごとにお得な情報を届けることもできるでしょう。
高い精度のデータを取得し、マーケティング戦略に活用したいのであれば、DX推進を検討してみましょう。
小売業DXの課題と対策

小売業にとってDXの推進は重要ですが、進めていくうえで下記のような課題もあります。
- 経営戦略の検討不足
- DX人材の不足
- 既存システムとの連携
- 成果が出るまで時間が必要
ここではそれぞれの課題について深堀しながら、対策方法について紹介します。
経営戦略の検討不足
1つ目の課題は経営戦略の検討不足です。DXの効果を最大化するには、デジタル化によって何を叶えたいのかを明確にする必要があります。目的が明確でないと、システムを導入するだけで満足し中途半端な結果に終わってしまうでしょう。
DXをスムーズに進めるには、目先の結果を求めないことが前提です。経営戦略に落とし込んだうえで5~10年後のビジョンを明確にして、地道に改革をしていく必要があります。
DX人材の不足
2つ目の課題はDXの人材不足です。小売業はそもそもの人材不足に加え、日本の企業全体においてDX人材の不足が懸念されています。情報通信白書の調査によると、約7割の日本企業において「DX人材が足りない」という結果が出ました。
参考:情報通信白書 総務省
したがって、今後企業ではDX化を進めるためのチーム作りや人材育成、専門部署を設けるなどの対策が必要になるでしょう。社内で人材確保や育成が難しい場合は、ITベンダーやITコーディネーターに相談して、専門的知識をもった人のサポートを受けるのも有効的です。
既存システムとの連携
3つ目の課題は既存システムとの連携です。蓄積されてきたデータは、いわば企業の財産であるとも言えます。DX化を進めるにあたってシステムを刷新する場合でも、それまでのデータを活用するには、既存システムとの連携や共存を検討しなければなりません。
ただし、既存システムの内部構造が不透明になりブラックボックス化していると、新しいシステムとの連携を図る際に大きなコストと時間がかかることもあります。必要なデータの取捨選択を行いながら、システム連携の方法を模索する必要があります。
成果が出るまで時間が必要
4つ目の課題は、DXの成果が出るまでには時間が必要である点です。DX化のために導入したシステムを活用して事業を進めていくためには、従業員のトレーニングやデータの蓄積に時間がかかります。人材や資金の大規模な投資も必要になります。
そのため、DXを実現させて業務効率化などの目的を果たすには、長期的な予算やリソース確保が必要不可欠なのです。DX推進の計画を立てる際は、短期的な結果を求めるのではなく、長期的な視点でプロジェクトを進めていくことが大切です。
【国内】小売業DXの事例

実際のDXの取り組み事例を、次の5つの企業を参考に紹介します。国内・海外それぞれ紹介します。まずは日本国内5つの企業の事例です。
- ローソン
- 無印良品
- スターバックスコーヒー
- イオンリテール株式会社
- 株式会社平和堂
セルフレジの導入やAIによる発注の自動化、アプリの活用などさまざまな事例がありますので、自社のDX推進の参考にしてみてください。
ローソン
コンビニエンスストア「ローソン」は、率先してDXを進めています。ローソンでは店舗用タブレットを導入し、毎日の発注数を過去のデータをもとに自動化しました。この取り組みにより、業務時間の短縮や在庫数の最適化、廃棄ロスの削減が期待できます。
またローソンでは現在無人店舗システム(Lawson Go)の開発をおこなっています。近い将来には完全に無人で、カメラやAI、生体認証を活用した購買体験ができるかもしれません。
無印良品
無印良品では「MUJI passport」アプリを活用して、DX推進を成功させました。MUJI passportには次のような活用方法があります。
- 店舗やネットストアで買い物をすると「MUJIマイル」がたまる
- たまったマイルに応じて「MUJIショッピングポイント」がもらえる
- 無印良品からお得な情報やイベント情報を確認できる
- 近くの店舗の在庫状況を確認できる
- 無印良品期間中にお得に買い物ができる
アプリを活用すると、ポイントをためられたりお得なクーポンをもらえたりするため、顧客満足度につながります。またアプリで在庫状況の確認ができるので、「店舗に足を運んだのに売り切れていて購入できなかった」といった顧客の不満解消の効果もありました。
結果としてMUJI passportは4年間で1,000万回以上ダウンロードされ、現在も多くのユーザーに親しまれています。自社アプリを活用して事業を拡大したいい例といえるでしょう。
スターバックスコーヒー
スターバックスでは2020年から独自のモバイルオーダーシステム「Mobile Order&Pay」のサービス展開を始め、DX推進を成功させています。
Mobile Order&Payは、事前にアプリで注文と決済ができるため、店舗に行ってからレジに並ぶ必要がありません。支払い額に応じてポイントが貯まるのも魅力です。
結果としてスターバックスの売上高は、コロナ禍においても順調に上がり続けています。モバイルオーダーやアプリの導入など、時代の変化に応じて改革を重ねたロールモデルのひとつです。
イオンリテール株式会社
イオンリテールでは、新しい買い物方法として「どこでもレジ レジゴー」を導入しています。レジゴーは2020年から導入が開始され、顧客自身で商品コードをスキャンしながら買い物を進める決済サービスです。
顧客は店内で貸し出される専用スマホを持ち歩き、商品コードをスキャンしながら買い物を進めていきます。そして対応する精算機に、スマホの買い物データを送信して会計します。
スマホでスキャンしたデータは買い物の途中でも見られるので、合計金額の確認や買い忘れ防止に役立ち、利用したユーザーからは好評です。また決済も店員によるスキャンが不要になり、レジ業務を簡素化できるため、人材不足の解消にもつながります。
「どこでもレジ レジゴー」は来客のおよそ2割が継続利用しており、今後も導入店舗を増やす予定です。まさにOMOを活用し、顧客に対する体験を提供しているDXの事例といえます。
株式会社平和堂
滋賀県を中心に店舗展開している平和堂では、DX推進の取り組みとして「発注業務におけるAI自動予測発注システム」の導入を進めています。
AIによる自動予測発注システムを使えば、販売に影響する情報の蓄積や分析が可能です。蓄積したデータを基にしてAIが日々の発注数を自動で算出してくれるので、発注時間の削減や廃棄ロス、欠品などを防ぐ効果があります。
結果として発注作業が2分の1程度になり、顧客とのコミュニケーションや魅力的な売り場作りに注力できるようになりました。在庫管理や発注作業の属人化を打破したモデルケースとして、参考にしてみてください。
【海外】小売業DXの事例

最後に、海外企業の小売業DX事例を5つ紹介します。
- Amazon
- Nike
- IKEA
- Netflix
- Uber
Amazon
1994年に創業したAmazonは、ECサイトがまだ一般的ではない時代に、書籍をインターネット上で販売するビジネスを始めました。その後「地球上で最も豊富な品揃え」を実現するためにECサイトの充実化を図り、今や小売業界をリードする多国籍企業となりました。
ECサイトではAIを活用したおすすめ機能で購買行動を促進し、1クリック注文機能で購入機会の損失を防ぐなど、DXによる小売サービスの進化を果たしています。
また、同社ではビジネス向けクラウドサービス「AWS(Amazon Web Service)」も提供しており、そのシェア率はトップレベルを誇っています。Amazonの取り組みは、DX成功事例の代表格といっても過言ではありません。DXという概念がまだ世になかった時代からの取り組みが功を奏した一例と言えるでしょう。
Nike
スポーツ関連用品を扱うブランドNikeでは、サイズの合う靴を提案するモバイルアプリ「Nike Fit」を開発しました。顧客がこのアプリで自分の足をスキャンすることで、データを収集して両足のマップを構築し、足に最もフィットする靴を提案するという仕組みです。
このアプリには人工知能やコンピュータービジョン、データサイエンスなどのデジタル技術が活用されており、DXによって顧客満足度向上に成功した事例だと言えます。また、収集したデータは商品開発に役立てることもできるようになっています。
IKEA
スウェーデンの家具メーカーIKEAではECサイトをはじめとしたオンラインサービスの向上によって、顧客満足度の向上を図りました。
具体的には、家具の購入や組み立てに関する相談ができるビデオ通話サービスや、AR(拡張現実)で自分の部屋に家具を置いたときのイメージを確認できるサービスなどを展開しています。
DX化により家具購入に関する不安を取り除き、購入前後でのギャップを減らすことで購買を促進し、顧客満足度向上にもつなげることができた事例だと言えます。
Netflix
Netflixは、オンライン上で好きなタイトルを注文することでビデオテープやDVDをレンタルできる、オンラインビデオレンタルサービスを始めた企業です。それまでは店舗型が一般的なスタイルだったレンタルビデオサービスの中で、デジタル技術を活用した画期的なサービスを生み出したのがNetflixなのです。
その後もサブスクリプション型のDVDレンタルサービスや、VOD(ビデオオンデマンド:オンライン上での動画配信形式)へとビジネスモデルを転換し、DXによって進化を続けてきました。
結果、現在ではサブスクリプション型動画ストリーミングサービスとして、世界でも高い人気を誇っています。
Uber
フードデリバリーサービスや配車サービスを提供するUberでは、スマートフォンアプリを活用してユーザーと配達員・ドライバーをマッチングするデジタルプラットフォームを提供しています。
Uber社で配達員やドライバーを雇用するのではなく、サービスを利用したい人が注文したタイミングで働きたい人とのマッチングが行われる仕組みであり、DXによって新しい働き方を生み出した事例であるとも言えます。
受発注から決済、利用後の評価まですべての操作がアプリ上で行えるため、ユーザーの手間が少なく、サービスの品質も継続的に担保しやすいといったメリットがあります。顧客や配達員・ドライバーの情報もデジタルで集約されるため、データを活用した事業の改善にも役立てることが可能です。
まとめ
小売業界では、深刻な人材不足への対策が早急に求められています。また利便性を求める顧客のニーズにも対応する必要があるため、セルフレジの導入やAIによる発注システムの自動化を進めることが必要不可欠です。
しかしDXの推進はデジタル化が最終目的ではないので、企業の目的を明確化して進めていくのが重要です。本記事で紹介したさまざまな導入事例を参考に、今後の経営戦略の一つとしてDX推進を進めてみましょう。
AI GIJIROKU ブログ編集部です。議事録や、会議、音声を中心に生産性を向上するためのブログを執筆しています。