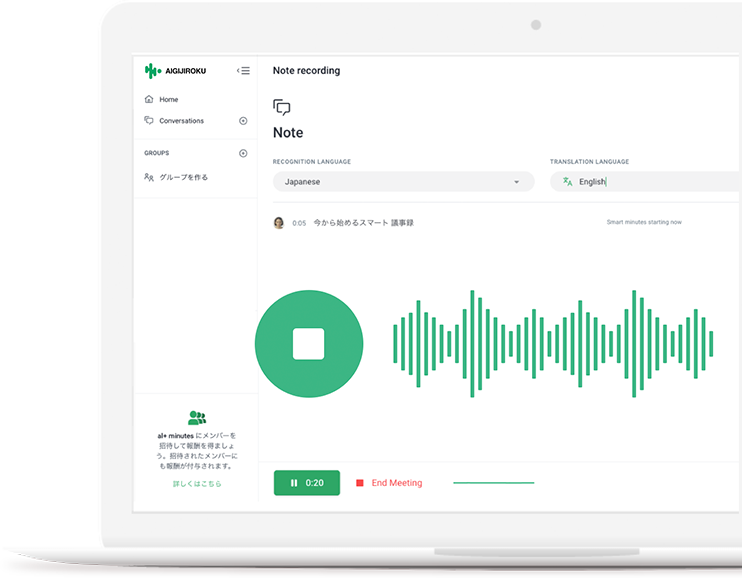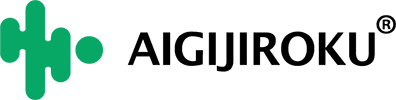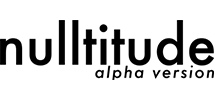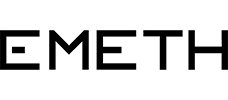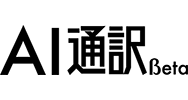働き方改革、テレワークの推進が進む中で、セールスのあり方も変わってきました。直接訪問する営業スタイルから、オンライン会議システムを通して商談するセールスのオンライン化が進み、インサイドセールスに注目が集まっています。
これまで主流だったフィールドセールスのテレアポも、効率性を求めて営業のプロセスも分業して成約率を上げることが可能になりました。
そこで今回は「インサイドセールスを導入したいけど、やり方や人選の配置がわからない」このような疑問について、インサイドセールスとは何か?新規開拓やテレアポとの違い、フィールドセールスとの役割分担についても解説していきます。
目次
インサイドセールスとは何か?
インサイドセールスとは、非対面で顧客対応を行う営業のことで、電話対応やオンライン通話のシステムを使った際に使われる言葉です。
これまで営業(セールス)は、相手と直接会って商談を進める対面式が主流でした。しかし、働き方改革の一つとしてテレワークの推進と普及もあり、直接会わずとも、オンラインで商談をしたり、契約を電子化したりする企業も増えています。
そのうちの一つであるインサイドセールスも、時代の流れに合わせた営業活動と言えるでしょう。
インサイドセールスを導入する3つのメリット
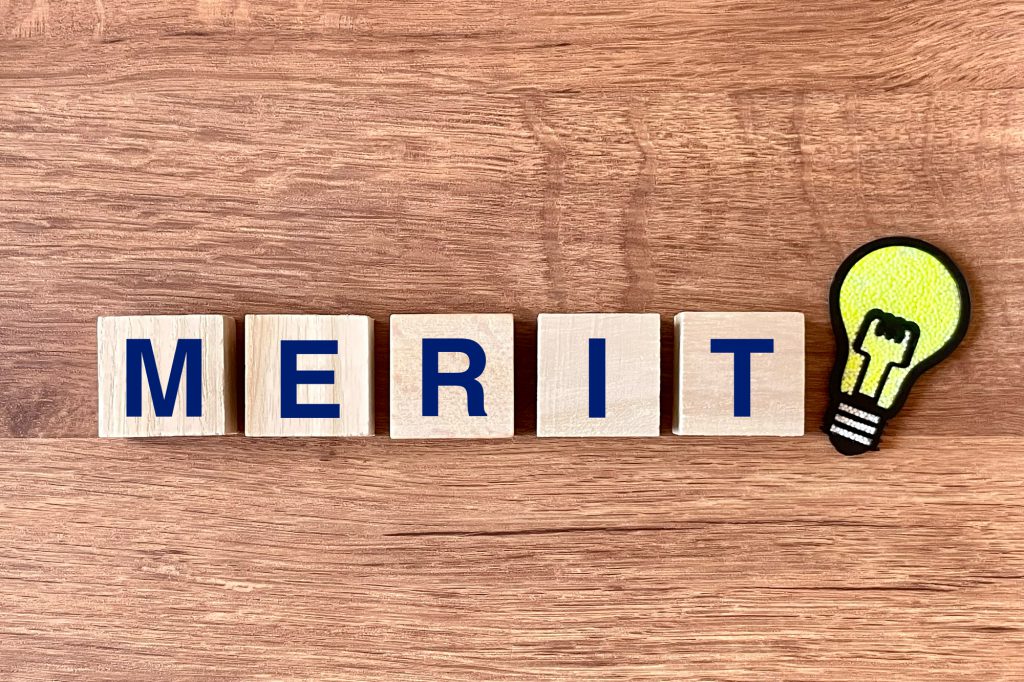
テレアポとインサイドセールスの違いでもお伝えしてきた通り、インサイドセールスには成果につながる期待が持てます。導入には一時的に変化が必要ですが、時間をかける価値があるぐらいのメリットがあると言えるでしょう。
この章ではインサイドセールスを導入する3つのメリットを解説していきます。
営業担当者の負担が減る
インサイドセールスを導入するメリット1つ目は、営業担当者の負担が減ることです。これまでの営業活動は、以下の認知から成約までを担い、業務量が増える傾向にありました。
- 認知(興味・関心を探る)
- 教育(商品の紹介)
- クロージング(比較・検討・不安要素を解消)
- 購入(契約等)
しかし役割を分担することで、得意なことに専念できる体制が整い個人の能力開発にもつながる期待が持てます。
初めての人や会社にアプローチするのが得意な人、セミナーなど認知活動で饒舌に話せる人など、営業活動にもメリハリが出てくるので、負担を減らすことでやることが明確になれば、個人のモチベーションも上がってくるでしょう。
関連記事:営業効率化の方法とは?活用するべきおすすめのツールを解説
見込み客の最適化ができる
インサイドセールスを導入するメリット2つ目は、見込み客の最適化ができることです。
見込み客でも取引に結びつかないところはリスト化せず、興味がある人を絞り込めるところが、インサイドセールスの魅力の一つでもあります。
業績だけを考えて無理やり顧客に買わせようとするのは、信頼関係を崩したり企業価値が下がったりするおそれがあるでしょう。顧客が自社を選べるように、自社も顧客を選んでいくことができます。
自社内の役割を明確にすることによって、見込み客となるターゲットをある程度決めておけば、行動指針も明確になり日々の業務が自然に改善する期待が持てるでしょう。
少人数でも対応可能|人手不足にも対応できる
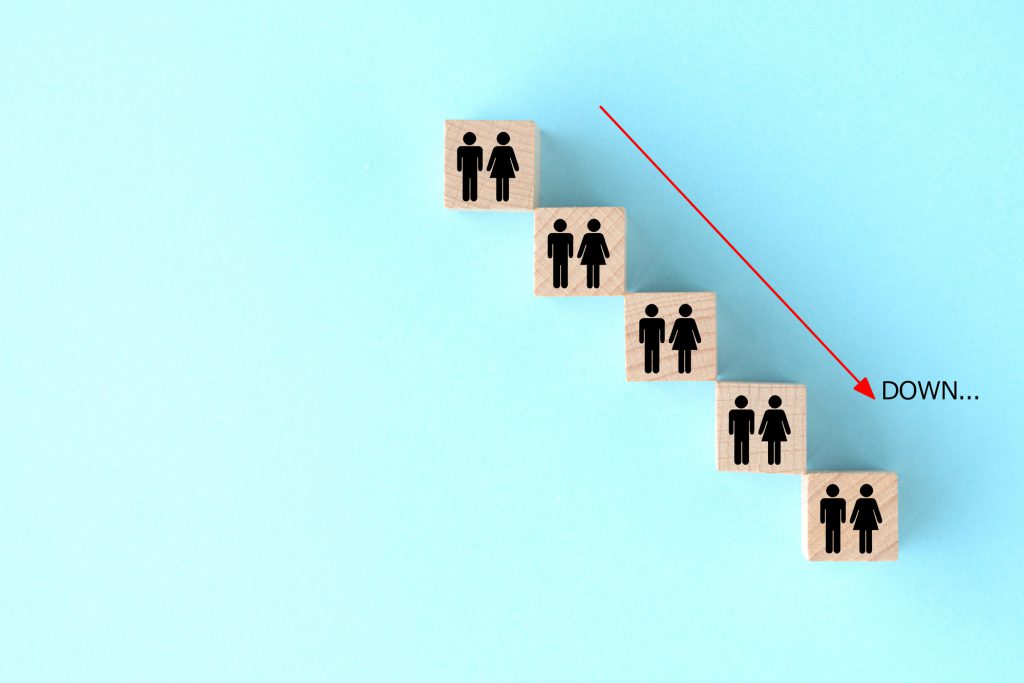
インサイドセールスを導入するメリット3つ目は、少人数でも対応可能なところです。
インサイドセールスは教育がメインのため、1人で同時に複数の見込み顧客を担当できます。これによって少人数でも十分に担えるでしょう。なぜなら、教育という役割が明確になっているからです。
分業によりその他のことは、別の担当者に依頼をすることが可能で、心と業務の負担が減ることが大きいでしょう。
一人の負担が減ることに加えて、人手不足に対応する効果も期待できるところです。やることを増やすより、やるべきことを明確にするから、やらないでいいこともわかります。事業の拡大はせずとも、既存の力で売りを最大限にするパフォーマンスを出すことが可能になっていきます。
インサイドセールス本来の力を発揮するまでには少し投資が必要ですが、負担減と効率化が可能、さらには成約率が上がるなら、投資していくべきと言えます。
顧客情報の一元管理で効率化
インサイドセールスの準備等が整ったら、顧客情報を一元管理できるようにすると、情報のズレが発生しにくくなります。必要経費として投資できるなら、システムの導入を検討するのもありです。
しかしながら、いきなり高額なものに投資するのは、使いこなせるかどうかという課題も出てくるので、まずは自社でルールを決めて運用していくことが、効率化に繋がります。
関連記事:インサイドセールスのやり方とは?取り組む際のポイントを解説
インサイドセールスで設定される代表的なKPI項目

インサイドセールスを導入する際は、評価指標としてKPIを設定しておくと、適切な効果測定が行いやすくなります。営業状況の改善を目指してPDCAサイクルを回していくためにも、あらかじめKPIを設定しておくとよいでしょう。
ここでは、インサイドセールスで設定される代表的なKPI項目をいくつかご紹介します。
架電数・架電率や通話時間
架電数・架電率や通話時間は、インサイドセールス部門において設定されるKPI項目の中でも代表的なものの1つです。1日や1週間などの一定期間内に行った架電数や、実際に顧客につながった回数(架電率)、顧客とのコミュニケーションが行われた時間の長さ(通話時間)を評価指標とします。
インサイドセールスを効果的にするためには、顧客との接触回数を増やして関係性を深める必要があります。これらのKPI項目は、そうした積極性や、有意義なコミュニケーションが行われているかどうかといった要素についての評価をするのに役立つと言えるでしょう。
開封率
開封率は、電子メールやメッセージなどによってコンタクトを図るインサイドセールス部門において、よく設定されるKPI項目です。顧客に送信したコンテンツが開封された割合が指標となり、そのメッセージが効果的なものであったかどうかを評価するのに役立ちます。
商談数・商談化率
商談数・商談化率は、商談(アポイント)を獲得した数を指標とするKPI項目です。アポ獲得数やアポ件数、商談獲得数、案件化数などと言われることもあります。
営業活動における最終的なゴールは、成約数を増やし売り上げを作っていくことです。インサイドセールスを見込み客の育成段階担当として導入する場合は、顧客との関係性を構築し、商談につなげた数や割合をKPIとして設定すると、適切な効果測定ができるようになるでしょう。
受注数・受注率
フィールドセールスとの分業を行っており、インサイドセールスだけで成約・受注までを担うわけではないケースも多いでしょう。しかし、その場合にも受注数や受注率をKPIとして設定することは効果的です。
受注数・受注率を指標としてとらえることで、見込み顧客の育成段階から受注を意識しやすくなり、顧客とのコミュニケーションの精度向上につながると考えられるからです。条件の合わない顧客との商談を回避しやすくなるなど、営業部門全体の労力削減も見込めるでしょう。
受注額
受注額や受注単価も、インサイドセールスのKPI項目として有効です。成約に結び付いた案件の受注額を数値指標として捉えることで、どのようなコミュニケーションを行えばより単価の高い商談成立につながるのかが把握しやすくなり、営業効率の向上につなげることができます。
インサイドセールスとテレアポの違いを解説

インサイドセールスと混同されがちな営業手法に、テレアポがあります。しかし、この2つは対象となる顧客やアプローチ方法など、異なる特徴を持った営業手法です。どのように違うのかを見ていきましょう。
テレアポは新規顧客への認知が目的
テレアポは、自社商品を知らない新規顧客に対して認知してもらうための活動です。この時点で見込み客と呼ぶ場合もありますが、自社の商品を知らない人たちへのアプローチとなるので、実際には見込み客というより「見込み客の発掘作業」になります。
テレアポの具体的な活動と目的は次のとおりです。
・新規顧客に電話によるアプローチを行う
・興味がありそうな顧客を見つけるため、アプローチ数を上げる
・目的は次の約束を取り付けるまでに留める
あくまでも目的は「認知」です。興味がない人へのアプローチはクレームの対象になるので、控えるようにすると、押し売り感が出ません。
また、興味がありそうと判断して、クロージングのように、購入を迫る対応は成約したとしても押し売り感があり、相手の印象に残りやすいです。ですので、顧客が判断しやすいように活動をしていきましょう。
一方で見込み客は自社商品に興味があり、購入を検討しそうな段階にある状態の人または企業のことを言います。その状態にある顧客に対してインサイドセールスの役割が明確になり、成約率が高くなります。
インサイドセールスは見込み客への教育がメイン
インサイドセールスの役割は、営業における過程で2番目の「教育」になります。
- 認知(興味・関心を探る)
- 教育(商品の紹介)
- クロージング(比較・検討・不安要素を解消)
- 購入(契約等)
見込み客への教育とは、顧客の悩みを自社でどのように解決できるか?を提案し、不安要素を消していく作業のことです。テレアポで見込み客の発掘に成功したら、次の担当が変わることに違和感を感じる顧客もいます。
ですので、インサイドセールスは事前に次のような見込み客を引き寄せる活動も必要になります。
・新規顧客でも取引を50%以上の確率で実施する予定
・インサイドセールスまでの接触回数を増やす
インサイドセールスを実施できるまでの、見込み客へと発展させる接触回数も重要になってきます。この場合は対面、オンラインどちらでも有効でザイアンス効果を出すために、顧客にとって必要な情報を投げかける活動が良いです。
反対にアプローチした時点で興味が薄い顧客は、関係が途絶えないようつながっておく意識のほうが興味のある顧客に注力することができます。興味があったり成約の意識が強かったりする顧客は、相手から質問等をしてくることが多いので、入念なフォローを心がけるようにすると良いでしょう。
インサイドセールスとフィールドセールスの役割分担

商材や業界によっては、インサイドセールスだけで営業活動を完結させることも可能です。一般的には、インサイドセールスとフィールドセールスで営業活動を分業しているケースがよく見られます。
分業する場合は、主にインサイドセールスが見込み客の獲得・育成や商談(アポ)獲得までを担当し、フィールドセールスがクロージングを担当するケースが多いと考えられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、分業して連携することで、より効率的な営業活動が可能になります。
ここでは、インサイドセールスにおいて考えられる導入パターンを解説しますので、導入の参考にしてください。
導入パターン①:見込み客の獲得のみ担当
1つ目のパターンは、新規の見込み客を獲得するフェーズにおいてのみインサイドセールスを導入するパターンです。この場合、インサイドセールス担当者は見込み客となる可能性の高いリード(潜在顧客)へのコンタクトを図り、ヒアリングや情報提供を行います。
電話やメール、オンライン商談を活用して営業活動を行うインサイドセールスは、フィールドセールスよりも多くの顧客との接触が可能です。そのため、より多くの見込み客獲得につなげることができるでしょう。
導入パターン②:見込み客の育成(リードナーチャリング)を担当
2つ目のパターンは、見込み客やリードに対する育成(リードナーチャリング)担当としてインサイドセールスを導入するパターンです。
見込み客の育成とは、継続的なフォローアップや関係構築を行いながら、彼らのニーズや課題を理解し、興味を持ってもらうようなアプローチを行うことを指します。関係性を築いてからフィールドセールスのクロージングにつなげることで、成約確度を上げることが目的とされています。
導入パターン③:クロージングやフォローアップまですべてを担当
3つ目のパターンは、インサイドセールスのみでクロージングやフォローアップまで含めて、すべての営業活動をインサイドセールスが行うパターンです。
営業活動をすべてインサイドセールスが担当する場合、フィールドセールスが商談を行うよりも多くの顧客とコンタクトを取れるため、より効率的な営業活動が可能になります。
ただし、直接会って対話するフィールドセールスとは異なる商談スキルが求められることも多く、慣れないうちは難易度が高い営業手法であるとも言えます。自社の状況に合わせて、より効果が高くなる導入方法を検討しましょう。
インサイドセールスの向き・不向きな人を解説

インサイドセールスを導入して必ずしも、営業担当から選ぶことが最適とは言い難いです。なぜなら、得意分野と個性がそれぞれ違うからです。また一方的な見方で適性を判断してしまうと、個人のモチベーションが下がることになります。
インサイドセールスを導入するに当たり、人選の基準も変えていく機会と判断すると良いでしょう。
インサイドセールスに最適な人を選ぶ4つのポイント
必ずしも対面能力が高い人が向いているわけではない。以下の特徴の人でも、得意分野が活かされる可能性が高く、個人の能力が開花する可能性もあります。なぜなら役割が分担されていて、やることが絞られているからです。その他の業務も信頼し合うことで、
オンラインでのコミュニケーションスキルが高い
インサイドセールスに最適な人を選ぶポイント1つ目は、オンラインでのコミュニケーションスキルが高いことです。
フィールドセールスなど外出が多い営業社員の中には、直接会うことで能力を発揮できる人もいます。逆にオンライン化を苦手とする社員も、一定数いることは確かです。
その点をマイナス要素とするより、活かすことにするのが良いでしょう。内勤の業務だからといって、コミュニケーションスキルが苦手とは限りません。社内での調整が上手くできる人は、顧客にわかりやすく説明できるという新しい一面も見られるかもしれません。
コミュニケーションスキルは、新規の人と話すのが上手、成約に結びつけることだけが高いと判断するのは、一方的な価値観になるので、幅広い視点をみることが大切でしょう。
クレーム対応能力・楽観的に捉えられる

インサイドセールスに最適な人を選ぶポイント2つ目は、クレーム対応能力・楽観的に捉えられることです。
インサイドセールスの対象となる見込み客は、信頼をある程度獲得できている分、期待を込めて話したり、要望が素になったりとストレートに言ってくる人も増えてきます。
真に受けると真面目さがマイナスに働いてしまう可能性が高く、自信喪失してしまい本来のスキルや能力を発揮できなくなります。一つの苦い経験が頭に残り、これまでできていたことも見えなくなれば、業務に支障をきたしてしまうでしょう。
個人や会社にとってもマイナス要素になるので、あらかじめ人選する際のポイントとして基準に入れておくと良いです。
反対に受け流せる能力がある「聞き上手」と判断した人を配置するのも有効です。ここで言う聞き上手とは、相手の話を最後まで聞くことが出来る能力のことを言います。
人は最後まで話しを聞いてくれて、言いたいことを出し切ったあとは、思考が空っぽになるので、アドバイスを受け入れやすい傾向があります。
タスク・事務処理を迅速にできる
インサイドセールスに最適な人を選ぶポイント3つ目は、事務処理を迅速にできるところです。対面で話すことが得意でも、事務作業のように一つずつタスクをこなしていくことは、苦手とする人もいます。
インサイドセールスは、入力作業も必要となる可能性があるため、対面能力と並行して事務作業のスピードも求められるでしょう。事務作業を得意とする人だったら、得意分野が役に立っている実感が湧き、新しい挑戦を自らしてくれる期待もできます。
また、役割が分担されて明確なので初見の人との接し方が苦手なだけで、親密な関係性を築けている前提がある人ならば、インサイドセールスを担当すると成果が期待できるかもしれません。
事実ベースで個人の意見を挟まずに伝えられる
インサイドセールスに最適な人を選ぶポイント4つ目は、事実ベースで個人の意見を挟まずに伝えられることです。
事実を正確に伝えることが求められるのは、憶測が入ると顧客のニーズをしっかりと把握できない可能性があるからです。インサイドセールスは教育という信頼関係を築く大事な役割もあるので、他部署にもつながる連携も求められます。
個人の解釈や気持ちよりも、全体性を考えたバランスを必要とする場合も多いので、事実ベースで報告をすることができれば、連絡不備などのミスを防ぐことが出来るでしょう。
インサイドセールスに向いていない人の3つの特徴

インサイドセールスの業務には向いていない人もいます。しかしながら、成長と期待を込めた一方的な思いと、人手不足による配置は本人のスキルを活かすことができず、計画していた成果につながらない可能性も出てきます。
そこでインサイドセールスには向いていない人の特徴を認識して、成功していく確信度合いが高くなるよう努めていきましょう。
コミュニケーションや対面する業務が苦手
インサイドセールスに向いていない人の特徴1つ目は、コミュニケーションや対面する業務が苦手な人です。社内でも対外的にコミュニケーションを取るのが苦手な人は、人選するべきではありません。成長のために配置してもギャンブル性が高く、転職を希望される可能性も出てきます。
このような方を仮にインサイドセールスに関わる業務にする場合、仕組みづくりや事務作業にしてみると良いでしょう。コミュニケーションが得意な人が好まれる風潮ですが、不得意としている人は、別の方法もあるということも、インサイドセールスの導入する際に、見れるようにしたい視点です。
新規開拓が得意な人
インサイドセールスに向いていない人の特徴2つ目は、新規開拓が得意な人です。
フィールドセールスでは、新規開拓が得意な人もいます。逆に得意分野の行動を制限してしまうことで、スキルを抑え込んでしまう可能性も高いです。
新規開拓が得意な人は、すでに知っている顧客よりも「新しい人」との懐に飛び込むスキルが長けていると言えます。敢えて制限はしないほうが、得意なことを消さないので、インサイドセールス担当にするには、本人の意志を確認した上で実施するほうが良いでしょう。
フィードバックを受けられない人
インサイドセールスに向いていない人の特徴3つ目は、フィードバックを受けられない人です。このような方はプライドが高く、自分のやり方や成功理論にこだわりが強く現れやすいです。
インサイドセールスでも当然のことながら、いろいろな顧客がいてこれまでの経験が通用しない相手も出てきます。インサイドセールスは信頼関係を築いていく途中なので、成約につなげる重要な役割を担っています。
信頼関係が築けなければ、その後の見込み客という状態も消滅してしまうので、スキルや経験だけを見て判断するよりは、細かい人間性も見るようにしたほうが良いでしょう。
まとめ
インサイドセールスのパターンは、自社の特徴に合わせて柔軟に変えていくことで、社員の負担減と能力開発、生産性の向上につながっていきます。役割を分担しやるべき業務が明確となれば、新しいチャレンジや投資をする余裕も生まれてくるでしょう。
インサイドセールスの導入には変化が必要ですが、時代に合わせたやり方や自社の分析を心がけていくと、自社に合ったインサイドセールスの導入方法が見つかってくるでしょう。
なお、インサイドセールスの代行をする会社もあります。担当範囲やコンタクトの方法などは提供する業者によって異なりますので、自社に合ったサービスがあれば導入を検討してみてください。
AI GIJIROKU ブログ編集部です。議事録や、会議、音声を中心に生産性を向上するためのブログを執筆しています。